■ダーティーな業界
佐藤:19才頃、寺山修司が大好きだった。ご存じですか寺山修司を。ガルシア・マルケスの『百年の孤独』からタイトルをまま引用した舞台。汐留で開いた演劇があったんです。4つの舞台(島)があって、真ん中にでべそのように伸び縮む大きな装置がある。観客は4方向に座り、4つの演劇を同時に演じているんだけど、客は4つのステージを同時に見ることはできない。4回観ないとその演劇全体を想像することはできない舞台構成で、寺山最晩年作です。
発注者が「あの演劇を観て感動した。」と言うものですから、舞台のスケッチをまま反転というか虚実というのか、その舞台(右欄参照)のような形を基に家に仕立てました。(雑誌の記録を観る)『建築文化』と『建築住宅』の編集者たちが気に入ったのでしょうが、表紙をかざりました。でも工事費はめちゃかかりました(笑)。
身の回りの住宅発注者は私と同様でお金はさほど持ってない。で、豪華な建築は造れない。俺はゼネコン出なので建築業界の金の動かし方を知っていました。で、ディフォルメ気味に語りますと、抱き合わせ発注したり、一方で、建築会社の株主にもなっていました。建築家と胸を張る前に株主になれるか、そこがポイントだと思って実践しました。
他方で安価な建築の例をいえば2000年完成の告げられた予算が一千万円だった千万家(せんまんいえ)。セル・フビルドなら出来ると思って提案したんです。そしたら現金が無くって、月々返済が4万円だと総借入可能の金が1000万円だと言われました(笑)。自営で3年かければ出来るでしょう、と銀行に行ったら「半年で完成しないと貸さない、」と、借入無理だと言われました。100でいいだろうと。模型で1000を4年間見続けてきたから、「〇が3つ並ぶ、これがいい!」と言うわけです。奥さんの実家から500万円もらった、そうです、いただくのも賢いと思います。お金が無い彼らは方々拝み倒すんです。お金が無い発注者と建築業界対応するのは面白いですよ。
今は円安と外材にたよる家づくりなので、安価で楽しい建築をつくるのは難しいと思います。91年の経済バブル崩壊から続く、いわゆる民間任せとなり、安普請がたち並ぶ世になりました。
2013年撮影動画
タント:家を建てられるお金を持っている人は少ないですから。工法とか考え方を研ぎ澄ましていかに低予算で作るのは大切ですよね。
佐藤:それはやり方が少ないと思います。お金持ちからいただく、自前で安価で造る、ツーリストに貸して返済が済んだら自分で住む、間貸しをしてしのぐ、それぐらいしかないのではないかな。今は造ることから遠ざかってて、各種手法は忘れちゃいました(笑)。
でも、建築家は正しい!いいこと言っているんだよ・・・みたいな顔をするのは嘘語りが多いと思います。建築家も建築産業の一員です、一業者です。業界自体がダーティーなものは変わってないです。中世〜近世期の昔なら不浄な民がなす生業ですね。今でいえば、分かり易いのは海外からの研修生制度。世の人々に目に付きにくいのは国内の飯場に暮らしている、彼ら下請け労働者とか山谷や池袋から人夫集めて土工にしたてて、建築業界を下支えしていました。それが建設業の長年の実態です、ですから私はとある建築家のような上澄みの綺麗ごとを言う気になれないです。
タント:僕もそう思います。
(参照:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ・令和6年10月末時点 外国人労働者数は2,302,587人で・・・ 国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%) )
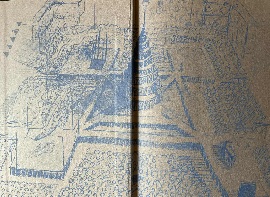
■建築基準法を変えた渡辺豊和さん
佐藤:現在の建設業界における下請け労働者の実態は知らないです。想像すると低貧国のアジアから集めて来て、プレハブの小屋にぶち込んで建設労働者にしているんだと思います。建築を構想した者が頂点に座り指示をだす、この構造で、社会がどうたらと言い張れるのか、分からない。重源が石風呂をつくり労働者を癒したように、法律を変えて労働者が働きやすく豊かになる方策を練るなら尊敬できる。けど、下請けの実態を知らないのは罪です。
渡辺豊和さんが尊敬できたのは建築基準法を変えたことです。耐震偽装して法律を変えた一級建築士もいましたが(笑)法改正によって次の建築の可能性を拓いたのは渡辺さんだけです、私の知る限り。木造建築は軒高9、最高だかさ13mだったかな、その制限を無くした。龍神村民体育館(1987年)を設計したとき、両方超えていた。法律など理解しないで、構想していたんだと思います。で建築センターに3年通い続けて許可を得て、造った。そのあと基準法が変わって、巨大な木造建築は誰でも設計できるようになったんです。
渡辺さんが初期に書いた『芸能としての建築』(1983年)をご存じですか? 建築家は芸能の民だと言っていたので好感をもったのも、交流し始めた切っ掛の一つです。
■建築史の研究者へ
佐藤:脱線しすぎました。現在においても濃いコミュニティーがあった魚村で育ったタントさんは貴重で研究者としてよいと思います。タントさんは建築史の世界に進路を変えたのは正解だと思います。業界をこなすタイプではない、と感じます。
タント:人をまとめられないので建築家にはなれないです。人も恐いし人望もないですから。
佐藤:人望なんてどうやって身に付けるのか分かりません。法螺貝を吹けばいいんじゃないですか。そして実現すれば徐々に人望もできてくるんじゃないですかね。
タント:僕は激情型で激しいんです。うまいこと法螺を吹けないので、失敗することが多いとは思います。
佐藤:もっと吹いてください、そのうち実現するでしょう(笑。コミュニティーづくりとか、法螺を吹く人いますけど、あれは実現しない。
タント:コミュニティーづくりも都市計画もそうですよ。
佐藤:うまくいかないと分かって法螺を吹き続ければよい。信じてそう言っている人が多いから、他人事ながら大丈夫なんかい?と観てます。
タント:田舎では建築家文化は認知されていないので、肩書や呼ばれ方いにこだわる人は少ないような気がします。
佐藤:雑誌掲載になると建築家と呼ばれるけど、自分では言わないですし、建築家の意識が薄い。
タント:そうなんですか。
(井の頭の話をしているが省略)
■重源
佐藤:浄土寺浄土堂を体験したとき、重源は建築家だ、と思いました。大阪で洋書店を営んでいた、故・大島哲蔵さんに車にのせられ案内されて知った建築でした。その後、閑谷学校にも行きました。1990年代は激しく、お互い交流してました。
重源の浄土堂はリアルとアンリアルが反転してて、いい仕掛けしてるな、と思いました。基壇が真っ黒の円で阿弥陀三尊像が超リアルに見えるような彫刻で、建築内部は赤と白で統一してて抽象的に仕上げている。反転手法は自覚しないとできないことです。東大寺再建の手法、お金の集め方、材料を見つける手法とかたいへんリアルで納得できます。巨大な檜を見つけたやつには褒美として米一俵だったかな?造るための手法もこの人は建築家だとおもわせます。
大田博太郎さんの『日本建築史序説』をひらくと、大仏様式がなぜ、消えてしまったか書いてありました。棟梁、大工さんたちは大仏様式を使いたくなかったので、徐々に消えてしまう、という内容だったと思います。重源に指示されて造作することはできても、従来の和様に戻してしまう、と書いてましたので同意しました。(104頁前後、「大仏様と重源」参照のこと)
重源は新しい様式を大工に作らせる能力はあり、そういう意味でも建築家だったんだなと思ったんです。(記憶を保存するためによんだ俳句「妄夏を 玄円に盛る 浄土堂」)
タント:後世に巨大なモノを造るときに、大仏様はぶり返すのが不思議ですよ。東福寺とか再建するとき、江戸時代に造る時の東大寺大仏殿とか、どうやってそのあと大工家で伝えれたのかな・・・と思ってました。
佐藤:タントさんはそういう目で古建築を研究できるからいいですね。俺は貧乏だから友達に連れられていくことで、古建築のオモシロさと魅力を体験するだけでした。仏教というフィクションも日本文化ではあるけれども信用できないです。経典も共有してないので、他の古建築に興味が湧かなかったです、古建築を見学に行かないです。
自分の妄想にお金を与えて実現するのは楽しいから、他者の建築を観てこいつを乗り越えたいとか、同じことやりたい、とか思わない。自分の建築の造りかたしか知らないです。
重源には興味が湧いたので大阪に行くついでがある時に狭山池を訪ねて池の周りを歩いて地形を体験したり、佐山池記念館を観たりしてました。あの安藤建築の暴力性には疲れた記憶が残ってます・・・・
二人で安藤建築について語り合っている(省略)町づくりについても語り合っている。
■建築家の幼虫は、親にとっては金食い虫
佐藤:わが家で開催していた建築あそびには講師で後に有名になる建築家の卵も来てました。今もっとも有名だろう藤本壮介さんについて語ると、建築家の卵について具体的に分かるかもしれません。
2002年6月1日に開催しました。集合写真は支援者以外は、参加者は東京からやってきた数名でした。藤本さんはまだ有名ではなかったので、福島市内からは誰もきませんでした。彼には東京からの新幹線と電車賃往復だけで、午後から翌朝まで語っていただきました。記録は公開してます。翌日、田中浩也さんがフォトコラージュのワークショップをして午後東京にもどりました。

藤本さんの記録作りを終えて公開してから、私とmy長女で旭川の藤本さんの家を訪ねました。my長女は医学生だったので、札幌で医師たちの学会がひらかれていて飛行機で先に行ってました。私は青春18切符を使って、札幌まで行きました。
my長女とは札幌駅で早朝合流し旭川駅まで行き、そこからはバスに乗って、停留所から歩いて15分ほど、藤本さんの実家である精神病院の現地見学をしました。
作業療棟は最初の作品です。理由は語りませんが入り口周りはやり損ねた作品だと思いました。2作目の入院治療棟は個性的な建築としても成功していました。その時は実作が2棟しかなかったんです。その後少しずつ増えましたが、藤本さんも事務所経営が成り立っていず、東京の中野駅傍にガールフレンドだと思いますが2人の事務所をひらいてました。わが家での講義はそういう時期です。
現地見学した時、お母さんが出て来られて、「うちの壮介大丈夫でしょうか?またお金送れといってきました」仕送りばかり続いていて・・」、不安そうでした。「御宅の息子さんは直ぐに世界の建築家になるから、ジャンジャン仕送り続けて、ください・・。」とお願いしたことがあります。
それから数年後に仕事を増やしつづけ、人気の建築家の道を歩みはじめ、今は世界的人気建築家の一人になられているのは誰でも知っていることだと思います。大阪万博の木造リングも総指揮をとっているのでしょうし、東京駅傍にたつ超高層の頂部もデザインされているし、仙台の音楽ホールもコンペでとりました。たまたまmy長男が東北大で日本史近世末期の研究者として勤めているので、市役所から藤本事務所の面々に、仙台の歴史教育係を頼まれたそうで、仙台の街歩きを藤本さんと所員のかたと実施したそうです。
翌日my長男から「おやじ、わが家でのこと訪ねたら、覚えてなかったぞ。」と電話がかかってきました。それはそうだろう、23年前の福島のような田舎町で語ったことなど覚えてるわけないよ、と応じておきました。藤本さんの実家のお母さんの心配と経済支援に疲れ果てて出てしまう言葉は忘れることができません。
建築家を目指す若者が居たら、安藤さんのように私が勤めていた、関西のゼネコンから支援を受けながら力をつける、などの商売の手腕は要ります。藤本さんの場合のように、自力で建築家の花を咲かせるためには、実家からの経済支援が不可欠なんです。
日本では優秀な建築家卵を探し出して育てるための政策はありません。政府が支援してもコストや成果を議会で問われるのが嫌なのでしょうね。建築家を育てる政策はないのが実情です。大学の教員としてシステムと共生するなどし、その営業・肩書を活かして仕事を得る者が多いのでは?。藤本さんのように大学に所属せず独立建築家として育つのは日本では奇跡に近いと思います・・・。
建築家を目指す者は、親に相当の苦労を掛けることを覚悟しなければなりませんし、苦労を掛けたから必ず建築家になれる訳でもないです。自身にも親にも、賭博のような投資を強いることになる、それを若い人に知ってもらって、どうしても建築家になる!と決意できれば挑んでみるのもいいかもしれません。
タント:似たような話を知り合いの親しい先生も言ってました。「アトリエにあこがれるのはいいけれど、生活の事とか、お父さんお母さんのことをちょっと考えてるの?分かっているのか?」と、仰っていました。
佐藤:そうですよね若い自分に賭ける決断を出来ない者はなれません。ひと握りの金持ちの子で、地頭がよくって、人付き合いが上手で、自己演出力も備わっている者しか有名建築家にはなれないでしょう。だから彼らは下々の者たちの生活や苦労を分かってはいない人や、天辺しか見えてない、下は見ない。そういう人達が町づくりとか言い始めたら信用できない。ごくごく小さな場所で、特定の人に向かって町づくりというならいいけど、一般人にむかって、日本人のための町づくり、とは言わないでほしいです。
タント:そうですね。
佐藤:移り住んで、小さなコミュニティーのために、とことん話し合って時間を掛けて地域づくりを続ければいい。建築家はやがて亡くなるだけで、町は永遠の残る。まだ生まれていない他者のためにも、謙虚に考えて提案しないと、今、流行で押し切っては拙いですよ。謙虚に余計なことは省き、町づくりしながら修正続けるしかないでしょう。
150年ほど前の江戸後期の文書を、現在の一般の人が読みこなせないように、100年後の一般の人たちが、2025年の私達の考え方を読み、理解できるとは思わないです。
その頃には「コスパがいい」、も使われない言葉になっているでしょう、考え方も消えている。横文字つなげて語るから訳がわからない話が多いです。コスパよく、見た目はキラキラ小山のてっぺん取ることを考えている若い人も見受けます。
相変わらず俺だけ喋りつづけてしまっていますね(笑)。話題を変えましょう。僕のような怪しいお爺さんとも、夜こうして語り合っている(笑)。
タント:私自体も怪しい奴なんですよ。
佐藤:俺はタントさんの話を聞いていて、怪しい、と思わないです。
タント:たぶん佐藤さんだから受け入れてくれているんだ、と思います。
佐藤:そうですか。俺が話を聞きたくない、と思う若者はタントさんとは違う人種で普通にいる多くの人なんだね。タントさんをいい人じゃんと、思う俺が異常なんだな。
タント:私はいい人ではありません。文学少年が、ままでっかくなっているので、闇深いんじゃないですかね。つまるところ、社会不適合の困ったヒトです。
佐藤:自分の闇が深いとわかっていれば立派なもんですよ。
タント:人を傷つけちゃうし、傷つけられやすい奴ですよ。高度成長期の苦悩教の学生みたいなメンタルがまだ残っている感じです。
■みんな夢でありました
佐藤:1970年以前の左翼学生は大学をゲバ棒などでぶっ壊して、果てに大学の先生になったりして、学生を指導している、最悪の世代だけど。あんなことやったあと、若者を指導できるもんですね。高校生だったので彼らを見上げてましたけど、ああいう事をしでかす輩の神経が理解できなかったです。で、現在も立派なことを抜かすわけです。タントさんはそういう人達とは異なるでしょう?
タント:左翼学生じゃないですけど、あのようなネガティブな斜めに構えた文化みたいなのが持ってます。
佐藤:森田童子の『みんな夢でありました』、を教えていただきて動画見ました。けれど何を伝えているのか分からない。自分にボンヤリしているのか過去に戻りたいのか分からなかったです。過去なのか現在の事を歌っているのか。
タント:闇なんです。
佐藤:あの詩のあいまいさにぐっと来るわけですね。
タント:ネガティブさというのは一般的に否定されますし、時には責められることもあります。昔に固執していて、未来を見ていない。ということは、バカにされることも多いですが、森田童子は「それでもいいのだ」と言っていると思います。私のような内向的な人間でないと理解できないと思います。
佐藤:人に未来は無いので、過去と現在を見つめるのはいいことですけど、それでみんな夢だった、とまとめるのはファンタジーかも。
タント:気持ちを整理しようとはするんだけど、そういう事を考えていること自体が昔に固着しているんですね。
佐藤:1970年代は社会人になって設計図描いて働いてました。けど、森田童子の歌は聞いたことがなかったです。
タント:普通聞かないです。
佐藤:森田童子が女性だとも知りませんでした。
タント:あれを聞く人たちはカルトな人達です。人気は一般的には無いです。
佐藤:人知れず亡くなったとは書いてありました。
タント:原節子と同じでよくわからないんですよね。突然この世から、公の場所から姿を消してしまった人です。
佐藤:突然消えてしまうのは格好がいいね。
話変わりますがタントさんと同世代の大室佑介さんをご存じですか。40代半ばです。仙台の卒制日本一位になって、今は津市白山町を拠点にし建築もアート制作でも活動しています。多摩美の飯島洋一先生のお弟子さんです。日本一とって修士も経てからかな卒業して磯崎事務所で働いてから独立した建築家です。奥さんのお爺さんの家を引き継いで暮らしています。
■タント夫妻の地元
タント:同じ県内ですが遠いですね。今、G父の整理をmyパートナーがしていますが祭りの見せ場的な場所に自宅兼倉庫なので、地元民がやっているコミュニティーの場にできそう。それは、いいんじゃないか、という話はしています。
佐藤:地元に住みついて建築史の研究するほうがよいのでは?
タント:いいかもですね。
(博士課程の話をし始める 一部省略 )
タント:関東大震災の復興とその建築の研究をしています。学生なんです。2割り引きの学割使ってます。学生なのに何もやっていないんです。どよ〜んとなっているときに佐藤さんに声掛けられました。
佐藤:これからは論文持ってないやつが大学で教えてはイケない事にするから、建築家にも論文さっさと書け!と言い続けてます。私は高卒なので書いてないですけど(笑。
タント:私も博士とってないのに大学で教えているんですよね。
佐藤:教えられる学生の身にもなってみろ、と言ってるんです。博士号ないのに教えるってのは、建築界の悪い事例の一つ。
タント:私が所属している大学も、博士持っていない先生いますね。実務家で。
佐藤:笑っている─ 博士号とったほうがいいですよ、頭の整理ができるし。
タント:ここ数年気持ちの限界が来ています。
佐藤:俺に読ませようと思い一所懸命論文書いてください。論文書きあげても誰も読まないんじゃないかな、そういう感想は持ってますので、余ってるなら俺に博論くれろ!と押しているんです。貴方の本棚の肥やしにしててもしょうがない。
タント:博士論文あげるとお酒かなにかもらえるんですよね。
佐藤:福島県の地酒と交換してます(笑)
タント:お酒呑めないです。
佐藤:酒呑めない博士には福島産の果物と交換だね。
タント:いいですね、では頑張って書きます。
佐藤:福島の果物とタントさんの論文のぶつぶつ交換しましょう。けっこう持ってますよ。布野先生には「お前、博論読んでもわからないだろう!」と言われています。大きなお世話されてます。
■FULL CHIN.jp
タント:なんかブログ面白いですね。
佐藤:俺のサイトの何を読んだんすか?FBですか。
タント:FULL CHINサイトあるじゃないですか、あれって面白いなと思ってまして、何で面白いかと言うと、昔、鈴木博之先生の本が、「整理されていない墓地と整理されていない古本屋は意外な発見があって面白い。」と書いていたように思います。今はネットが凄い整理されていて、しょうもない文章を入れちゃうだけでも綺麗に見えちゃったりします。
佐藤:最近はAIが書いてくれるし、要約と整理してくれるし。ますます綺麗になりそうだね。
タント:ネットに出てくる詰まらない広告とか、整理されてるようにそれらしく見えるのに全然価値がないものばっかり、なんですよ。 佐藤さんのブログには鈴木博之先生が言ったような面白い乱雑さがあって、それを読むと凄い面白くって(笑)。
ある記事をある先生に関係あるから見せてあげたら、「ああ、私の知らないこと書いてある!なんだこんなこと、あんたよく知っているわね、」と言われました。
そういう発見があって(笑)面白いなと思ってました。私は建築にはあまり知識はないってことを理解しました。建築のそのものというより、周辺が興味の対象なのだと思いました。それを整理するためにnoteの記事を見本に書きましたがちょっとした進歩です。
佐藤:今世紀に入ってから25年、win95が普及して30年経ちましたので、旧来の発信方法じゃなくて、書き続ければいいんじゃないですか。ためになるけど面白くないのはもうやめて、面白いけどもためにもなる、それを書く。高度な技術が要るかもしれないけど。書いてて自分がオモシロいと思えばいいし、面白くなければ書かない方がいいですよね。
タント:ここ数年面白いと思ったのは測量ですかね。仕事の関係から。測量のプロと交流が始まって業界誌に2頁もらって、測量に使う近代建築をこの2年連載しました。あそび過ぎたかな?(笑)今反省しているところです。
佐藤:そのうち役立つでしょう。博士課程は8年まで所属OKで、満期退学になるんでしたかね?
タント:私は6年ですかね。3年経過してしまいました。生きる気をすわれています。
佐藤:まだ3年あるから、俺と会ったのが運の尽きで、論文書け!ですね。俺が定期的に言えばいいだけだね(笑)今日のようなオンライン駄弁りを2月一度はやりますので、書け!と毎回いいます(笑)
タント:本当にやってもらえるんですか。知識無しの男でもいいんですか?
佐藤:俺、ワイワイ相手の知識の有無を判断できる能力ないです、日本語をしゃべっているからいいです。このようなご縁ができたら、先が短いですけれど死ぬまで定期的に聞き取るだけです。いろいろな人に聞いてます。これは凄いという人は知らないですよ、私に知識が無い証です。でもこの人は面白い、と思う人だけ定期的に聞き取りを続けていました。また、「こいつは面白いから聞いって」と他薦されたら聞き取りに行ってました。今は足代も無いので、一度会いに生活の場にいってワイワイしたら、その後はオンラインです。
雑談しはじめる省略・・
タント:今日、切符を買ったときに、みどりの窓口が1ヵ所しか無いので、切符を買うのに20〜30分も掛かるんです。昔の国鉄だったらこんな事は起きないだろう!と思いました。
佐藤:webで買うしかない?パスモで買うとか。
タント:学割はwebで使えない、駄目なんですよ。
佐藤:あ、そうなんだ学生を締め出しているんだね。流行ってない、混雑してない駅で買うとか?
タント:場末だとみどりの窓口が無いんですよ。
佐藤:あそう?、辺鄙な所にみどりの窓口おかず、人件費節約してるんだ!国鉄時代とは違ってますね。学生と庶民にみどりの窓口を使いにくくしているんだね。
タント:例えば私の近所で大きな駅は北千住なんです。北千住はJR東日本なのでJR東海や西日本の新幹線の切符がかえられない。
一端休憩する
佐藤:本当にお酒呑めないんですか?
タント:ちょっとビールは呑めますけどね。
佐藤:今、呑んでください。
タント:この1週間で佐藤さんの作品をオサライして勉強しようと思ったんですけど、忙しくって申し訳ないです。
佐藤:俺の情報を知るなんてのはどうでもいいことですよ。
聞き取りしていて、博士論文書けなくって悶々としているオーバードクターのような50才前も、一杯いましたよ。「おまえ書けばかやろうが、書いてしまえ!」と関係ない爺さんに言われて、博士課程に入りなおして書き上げたりしているね。俺に会った人はみな書いているから、タントさんももう大丈夫書けちゃいますよ。これだけ喋って、定期的に喋っている間に書けてしまいますよ。皆定期的に会いに行っていると、書き上げてますよ。目次だけでも書け!っていいますからね。
奥さんでもいいんだけど、友達でもいいけど、「書け!書け!」と囃し立てる外野がいないと書けないんだね。先生に尻たたかれても、起動しないでしょうね。
■外国人に教える
タント:そういえば、外国人が8割もいる教室で教えることがあります。
佐藤:何語、英語、日本語で教えるんですか。
タント:日本語ですけど通じてないですね。
佐藤:先に出た話に続くけど、日本に来ている外国人に対して、だれも日本語教育をしない、という環境が日本なんだということですね。
タント:建築業界の人が経営してない教育施設だと外国人向けの建築教育についてのマスタープランが明確ではないかもしれません。
佐藤:日本語喋れないのに?教えちゃっている(笑)。都心の大学事情はしらないけど、早稲田大学は中国系の外国人に以前から大人気だ、と知り合いの先生が話してたのは10年ぐらい前でした。
日本の大学は少子化対策で外国人を入れることに文科省は舵を切りました。ので知らないけど留学生が増やして学校経営のガソリンにしてるんでしょう。学校経営もアメリカ流に成っちゃったんですね。なるほど。
タント:現在建築業界は空前の周知の人材不足なので、現場監督ならどこにでも入っていけるといった印象です。
佐藤:だから日本人で3Kの建築業界に入る若者もいなくなり、円安誘導もあり、コストプッシュで建築単価が爆上がりしているんだね。
日本語が分からない外国人労働者が日本語で書いた図面見て建築、造れるのが不思議ですね。建築業の技術は世界共通になってやっているんでしょうね・・。
タント:学校の話ではありませんが、最近身の回りに中東系の解体業の人をいっぱい見かけます。この間彼らが近隣の家を解体していたんです。論外だなと思いました。防音壁がないとか、全部壊し混廃でどこかに持って行ったり、道路に泥引きずりますし。
佐藤:解体でも分別せず、解体で周りを汚す、騒音だす作法は社会問題を起こしそうですね。
タント:困ったことにこういう話をネタとして使っている人がいますよね。例えばこの件で思い出されるのは、川口にいるクルド人ですが、実際はどんなものかは分からないです。トルコ人と言っている人たちがクルド人かもしれないです。インド料理屋ってネパール人がやってますが、インド人と区別つけられない、そういう話みたいです。
佐藤:外国人技能者の受け入れ政策がないなか、日本人とは宗教も暮らし方も違うし、風習もインドとネパール、クルドとトルコなどは日本人で区別つける、見分けられる人はいなさそうですね。東京都は高齢者も14%ほどで184万人突破、人種も複雑に入り混じってなんとか動いているという感じがしてきました。都心の外国人下請け労働者の差別的状況は、福島に暮らしていると分からないです。
雇用者が語る例、建設業の外国人労働者について34分あたりから。
その3へつづく