タント:こんばんは。聞こえてるのかな?
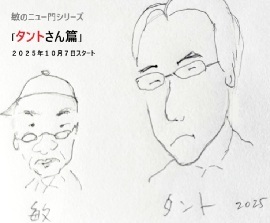
佐藤:聞こえてますよ。どうもどうもお忙しいところお付き合いいただきまして。
・・・タントさんPC調整している。・・・聞こえるようになりました?・・・ハウリング激しい・・調整している・・・・これでどうですか?
佐藤:ハウリングは消えました。これで大丈夫です、よろしくお願いします。
タント:こういうこと初めてなので。
佐藤:聞き取りは初めてなんですね。9月27日とある場所で偶然お会いして、聞き取ることになりました。縁があるようです。私は初対面の方に聞くのは気にならないので何でもお聞きします。
タント:私もそういう人達に助けられて、なんとかここまできました。
佐藤:メッセージ交換しているだけでは理解できない。「人生暗い」を演出してるのではないか?現在何が大変なんですか? メッセージでは全体がわかりませんでした。負債を背負っちゃったんですか、負の遺産を受け取ったんですか?
タント:いや、人生変わり目なんだと思いましたね。
佐藤:タントさんの人生も分かってないのですが・・・。
タント:負債はないんですが、私はポジティブではない性格なんです。極めてネガディブな下向きな性格なんです。
■パートナーの父亡くなる
佐藤:賑やかでなくっていいじゃないですか。
タント:遊んでくれる人は、「お前それはセコイよ!」といろんな人に言われるんです。暗さを前面に出すから、お前はそういうプロモーションのやり方だろうと。実際は、本当に「生きているのは嫌だ」とナチュラルに考えていて、そのネガティヴさを吐き出しながら、色々な人と、SNSなどでつながりました。佐藤さんのアカウントもチラチラ見ていて、ブログを拝見して名前は存じ上げておりました。
佐藤:ありがとうございます。自分のためのwebサイトですが、利用いただきどうもです。
タント:ネガディブ男なんですけれども、それに拍車をかけるように先月初めmyパートナーの父(以下G父)が亡くなりました。あまり帰らなかった故郷に行くとか、タント夫婦が別居とかになりました。
G父はベニヤの販売をしてました。ベニヤ板を仕入れて土地の大工さんに運ぶのがG父の仕事でした。誰にも引き継ぎしてもない。譲り手もないまま、それらがどうなってるのか?分からないまま、亡くなってしまいました。商売の中身が分からなくって、例えば広告の裏に走り書きで、帳面にして、メモらしき物を見つつ、G父の取引の全体を復元しています。つまり、G父の頭の中が事業のすべてで、それを復元してる最中です。
佐藤:それは大変ですね! 復元できないでしょうね。売掛金、未収金などは、帳簿がないと、再現不可能に思います。では資金回収はできそうにないね。
タント:G父は高度成長期零細自営業者として、そのまま生きていて・・その当時の建築生産現場の一側面を見て、生きた化石をみているような気分です。
佐藤:どんぶり帳簿で、今まで潰れないで・・・商売もちましたね、エライ!
タント:地元の大工にとっては、G父は使い勝手がいいんです。ベニヤ板一枚足りなくなったときに取りにいける。いい意味では「お人よし」、付け払いも有ります。平成20年(2008)に50万円分のベニヤ板を売ったんです。それを付け払いにしていて1500円ずつ返済してもらって、2025年現在15万円、100ヶ月残っていますこれからどうやって集金すればいいんでしょうか(笑)。
佐藤:地域の大工さんにとっては好ましいG父じゃないですか。
タント:そうです、だから葬式には会葬者が200人ぐらい来たんです。G父は地元のいろいろな無償の役員をやっていたんです。ひと昔前の地域の建築産業ってこうだったんだろうなと思えました。
佐藤:住んでいる福島市には現在ベニヤ屋さんなくなったような気がします。潰れて久しい。G父は2025年まで昔のままの商売をされていたと・・・それは相当凄いんじゃないですか。(参照:17世紀、越後屋が「店前たなさき売り」と「現銀(金)掛値なし」を始めた)
タント:地元の取引業者に聞いても木材関係で仕事をはじめても残るのは1〜2割だそうです。耐えられなかったり、飽きたいと。G父は鍵も人に預けられているとか、そういう人間交流のレベルの厄介事も多数引き受けていたようで遺族としては、附帯(?)した関係も洗い出さなければいけない状態です。
佐藤:鍵を預けられてしまうと、信頼関係を壊したくないから、ベニヤ板を盗みに来たりしないんだね。
タント:地縁という強烈な担保があるので、店の中はぐちゃぐちゃで分からないですが、隣の人に聞くとよくわかるんです。あるいは取引業者の方が、うちの倉庫の中に何があるのかよく知っている。このようなベタベタした地縁が、日本の伝統地縁なんだなと改めておもいました。今日の言葉で言えば「コミュニティー」でしょうか。
佐藤:今日までの聞き取りのなかで、人が好いパパが賭け事を仕組まれて、商売している家(旅館)を乗っ取られて、夜逃げせざるを得なくなったという話はありましたね。
タント:ベニヤ板だから、旅館のような家や土地を召し上げる旨味はないんじゃないですかね。
佐藤:G父はベニヤ板でなくって、家屋敷などの権利書を持たず、財布にも金が入っていなかったのかな・・・。1500円売掛して45年かけて回収しているような商売しているんじゃ〜、金持ちになれないね。
タント:昭和の帳簿が出てきて。毎月2000円ずつ5年間で償還、それがあたりまえに書いてあって、笑うしかありませんでした。
佐藤:そういう話は身近な請負師から聞いたことないですね。G父は貴重な人ですね。そういう建築文化が残っていたのは。
タント:とはいえそれはG父のオリジナリティーだとかしか言えません。
佐藤:G父がタントさんの地元の大工さんを底支えして2025年まで持たせたということでしょうね。G父が居なくなったら大工さん総潰れ!になっちゃうんじゃないかな?
タント:そうなんです。残っている大工40人ぐらいのために、ずるずると商売していた感じだったんです。
ベニヤ板は建築以外にも、鋳物をつくる砂型、その前の木型に使用します。そういう訳で「木型屋」にもベニヤ板を卸していました。地域柄、数社ありました。40ミリの3×8版があって、どうやって運んだのか?・・・知りたいところですが、もうわかりません。建築を勉強しているので、建築材料の多様な用途について、もう少し知りたいと思ったのと、考えが及ばない世界の広がりを思いました。建築の幅広さはこういうところにも垣間見れると思っています。
佐藤:最近はやりのCLT(クロス・ラミネート・ティンバー)材は扱わなかったんですか。た単なる合板を売っていたんですか?
タント:伝統的な単なる合板を売っていたんです。
■G父には大工さんが家族?
佐藤:G父は地域の大工さんを長年支えたと思うけど、笑われるような事ではないですよ。感心しますね。
タント:感心しますけど・・・遺された者のことも考えてほしい(笑。
佐藤:G父は大工さんが家族だったんですよ。
タント:そうですね。地域の数々のボランティア・マンでもありました。myパートナーはG父の事業の内容はわかりませんし、単価がいくらとか、締めの日などもわからないのですが、取引先はウソをつかずに、教えてくれるし、事業整理を手伝ってくれているのですから、結構なことだと思います。それにさっき言った1500円は今月も回収できました。
佐藤:G母は生きてはいないですか?
タント:G父が亡くなり、G母は痴呆に拍車がかかってしまいました。G父が亡くなり、転んでG母が一人でいるときに、寝床まで行けず、骨を折って病院に入った。myパートナーにすれば父が亡くなり家はいきなり空き家状態になってしまいました。骨を折ったのを契機にリハビリ施設に入りました。
佐藤:G母にとっては分からなくなってしまうほうが、悲しまずに済むので幸せな気がしますが・・・。
タント:82才で亡くなりましたので、葬式の日も「G父はどこに行ったの?」と5分に一度ぐらい、聞いてきました。老人の世界や地方の社会から離れて東京に暮らしていたので、それらを一気に見せられた後に、東京のキラキラしたインテリの皆さんやインテリジェンスの塊で出来た建築を見せつけられてしまい、「あ〜??!!」と思うわけです。言語化できないギャップを感じます。
■渡辺豊和さんのお別れ会
佐藤:まあね、G父母の旧来の愛情の様を聞いて、8月23日(記録へ)にあった大阪での「渡辺豊和さんのお別れ会」のことを思い出しました。1987年からの付き合いだったんですけど、今年の4月に亡くなってたんです。話に出てるG父・母とは逆タイプのご夫妻でした。奥さんの手厚い生活、金銭的にも支援。晩年は介護されて「・・現在の私(豊和氏)には極楽浄土の阿弥陀仏であり、時には空海の眞言宗曼荼羅の大日如来・・・」と書き残して亡くなりました。奥様は豊和さんにとって大日如来であり阿弥陀仏に一生守られて、過激な建築を設計し続けた建築家でした。
タント:秋田市の体育館が有名ですよね。
佐藤:集大成感はありますが、推しのいい建築はあれではない、と思います。豊和さんは口も悪いし、現実離れしていたし、奥様に守られていても生活感がまるでない。誇大妄想を語り、幻想の中に生き抜いているような面白い建築家の一人でした。バブル経済下の日本の幸せな建築家の成果、その一例だと思います。それをずっと観ておりました。
G父さんの場合は彼が菩薩で、Gママが現世の幸せな女性のコンビだと思います。でGパパが亡くなるとG母は現世や世俗世界を離れてしまった、と受け止めました。どちらの夫婦も互いの理想を生き続けお仕舞になる、幸せな形なんだなと、お聞きして思います。
■パートナーに甘える生活15年
佐藤:結婚されて何年?経ってるんでしょうか。
タント:15年ぐらい前です。出会いは私が16歳でした。myパートナーは高校の一つ上、吹奏楽部の先輩です。ですから、お互い幸せな結婚をしているんです。トロンボーンを吹いてました。横でmyパートナーもトロンボーンを吹いていました。myパートナーは二級建築士は取得していて、厨房機器メイカーに勤めています。
佐藤:福島県内浜通りに厨房機器の工場ありました、縁あるかもですね・・・3・11後の工場のことは分からないです。福島県とご縁ありますね。
タント:たぶんあります。白水阿弥陀堂へ行きたいです。会津若松の栄螺堂にも行きたいです。
佐藤:会津若松は松坂藩から移封した蒲生氏郷が基盤をつくった街もあります。東海道のメーインストリートのシティーボーイ・・・(東海道の話をしはじめてしまう佐藤)宮宿から桑名宿までは海路もよさそうだ。
タント:伊勢神宮の式年遷宮の御用材は、木曽川で流してきて桑名城のお堀で一時的に貯木場にしていたそうです。川を使ってながしていた、戦前まではそうだったようです。(参照:式年遷宮の御樋代木、写真が語る愛護の川流し桑名で20年ぶりに展示─朝日新聞ウェブサイト。他に桑名市博物館サイト、桑名宗社、を参照ください)
佐藤:いい事を聞きました。そうなんですか! さすが日本の古建築詳しいですね。
タント:三重県知事などが来たらしいです。今はトラックで木材を運びますが、桑名に到着すると人力で祝いながらトラックをみんなで引っ張ります。バックできないトラックが運んだと記憶しています、違ったかも・・・。名古屋近隣では結婚式のときの嫁入り道具を戻らないトラックで運んでいるとです。(笑)
佐藤:初耳、戻らないトラック、いろいろ勉強させてもらえて嬉しい!
タント:戻らないトラックに載せて木材がやってくる。他に石取祭の山車が特別にお迎えします。


G父は昔、会長。
■モラル・ハラスメントしつつ甘えながら
佐藤:タントさん夫婦の話にもどりましょう。高校時分からトロンボーン、趣味が一緒では別れないですよ。共通の音楽を理解し合ってる、強い絆ありですね。
タント:僕がモラハラ男のところがあります。いい加減ですし、子供といいますか・・。精神年齢が低い(幼い)んです。横暴かもしれません(笑)。myパートナーが怒ったら捨てられてしまう(笑)。
佐藤:大笑いしている。それはいいね。捨てられたら困るから泣きついて謝るしかないね。
タント:泣きつくしかないんですよ。生活していけない。生産能力低いですし、生活能力も低い。これらは、「ネガティブ」の具体例です。
佐藤:そんなことは長い付き合いだから分かっているでしょう。
タント:そうなんですよ。だからひどいことに安心して甘えちゃっておるわけです。
佐藤:甘えられる相手がいるとハッピーですな! それはいいや。トロンボーン吹いて、甘えていられる、いいこと聞きました。
タント:相手にとっては酷いことだと思います。よく持っているなと思います。10年以上も月1500円ずつ借金を返すのと同じです。
佐藤:G父が亡くなっても、取り立て屋は押しかけてこない、そんな気がするからいいんじゃないですかね。
タント:それは本当にそうです。
佐藤:G父は支払いはきちんとしていたけど、売掛の取り立ては極めて大らかに対応してたので、大工さんから好かれている「好人物だった」、ということですね。
タント:残されたものが売掛金の回収をしなければいけないのは困っています。佐藤さん、1500円ずつ返す債権を半額で買いませんか? そういう地縁の塊みたいな地域で育った私ですが、やはり東京に来てもいわゆる「下町」や「場末」を好んでしまいます。東京に来てから住んだのは常に「右半分」で谷根千などを地元と変わらないと思っていました。背の高い建物が嫌いです。
東京の荒川と中川の挟まれた下町情緒が残る落ち着いた環境で、個人商店、昔ながらの飲食店などがある、下町に借家があります(笑)。地域の建築系の文化遺産は旧小菅刑務所庁舎ですかね。あまり注目されませんが取り壊される予定の葛飾区役所庁舎(佐藤武夫設計)も文化遺産だと区民の皆さんに思ってほしい。
AI:夫のモラルハラスメント(モラハラ)は、精神的・言葉の暴力によって相手を支配しようとする行為で、被害者は孤立や自尊心の低下を招きます。夫にモラハラを受けていると感じる場合、状況に応じて弁護士への相談や、離婚に向けた準備を検討しましょう。?
モラハラ夫の言動の例
自分が悪いと思わず、何でも相手のせいにする
相手の意見を否定し、一方的に自分の価値観を押し付ける
相手の人格を否定する言葉を浴びせる
相手が反論すると、逆ギレして怒鳴り散らす
■社寺をまわる高校生
佐藤:話変わりますが、大学も奥様と一緒でしたか?
タント:大学は違います。高校が大きくmyパートナーは商業科にいました。当時は「コギャル」が流行っていました。東海地方なので、名古屋の派手な感じの女子高生が大半を占めていました。スカートが短くルーズソックスをはいている女子高生しかいませんでした。
しかしmyパートナーはかなり保守的で高校で唯一ひざ下のスカートでルーズソックスでもなく黒髪でした。逆に目立っていたように思います。芯が通ってないとできない昭和を続けるスタイルでした。(笑)
私も流行に乗らなかったので、地味だったと思います。私は生まれたのが一回りか二回り遅く、ネガティブなのがかっこいいというような、時代錯誤な高校生でした。それに図書館に籠って政治や藝術の話をしていたと思います。とりあえず、前は見ない常に後ろを見ていました。高度成長期に私が大学生だったらモテたと思うんですよ。
「寺が好きだ・・。」みたいなことを言う高校生でした(笑)。当時はだれも認知していない、御朱印帳と小銭専用の自作の巾着をもって寺社を回っていました(笑。学校では現代音楽を聴く面倒な生徒で、コルビュジェ持ってきて、ニーチェだとも言っていました。myパートナーは現実から逃避している駄目な奴を見て、これはどうにかしないと、死んでしまうと思ったらしいです。
佐藤:世話好きなんだね。駄目な大工を世話するG父のように、パートナーさんは駄目な男を世話するんだね。なるほど。
タント:今もダメですね。生活能力がなく、生きている気がしません。
佐藤:駄目でいいんじゃないですか。今はイケてる人は怪しいと私は懐疑的です。イケてるように見せているだけで、イケてないが、本人はイケてると思い込んでいる、困った人が多くなりました。建築家界にも多いイケてる輩には近づかないです。
タントさんを面倒見ようとする世話好き女性はいいですね。私には男女共学の高校は無かったですから、共学内部の男女事情もわからないですね。
女性に囲まれタントさんのような高校生活いいですね、それでもつまらなくなったら、ニーチェに逃げ込めばいいし。
タント:いまだに変わりませんが、文学ならゲーテとかニーチェ、音楽ならマーラーとかワーグナーに逃げ込んでました。悲しくなるとマーラーを聞いてこの世を嘆きます。もう生きていけないと思ったり、ピンチになるとワーグナーを聞いて大音量でかけて、何かよくわからない大きな力が働いて”わし救済されたい”と夢想します。とりあえず人生の隠喩ととらえたい(笑。こうやって救済されるんだな・・・という気持ちになるんです。
佐藤:港町で大海に面して爽やかな風もあるのに、どうして暗い、救済されたい気持ちになったんでしょうかね?分からないです。実家が暗かったのかな・・・。
タント:myパートナーと実家と私の実家は700mぐらいしか離れてないんです。myパートナーの家は城下町にある商店街で旧街道沿いです。一方で僕の家は漁村、正確にはその近傍なんです。こんなに近いのにまったく集落としての形態が異なり、人の雰囲気が異なっています。私の町は戦国時代に形成されていて、城下町ができる前から戦国武将から逃げてきた半農半武のような民がつくった地域です。網野善彦のいわゆるアジール論の無縁みたいな所から始まっているんです。
要は海浜によくわからない人が住みついて勝手に自治を始めちゃって、漁民をやりながらある時は武装して・・・藩ができる前からそれがあった。いまだに独特の食べ物もあって、私の親の小さい頃、高度成長期までは貨幣経済(西欧資本主義)が成立しておらず、おカネがなくても生きていけるような感じだったと聞いています。
佐藤:生き物を獲る人たちなど暮らす「部落」といわれるような形態ですか。
タント:出入りの少ない集落と言った感じです。先祖は中世的な、土豪の家来です。歴史的には近くの漁村との交流で成り立っていたらしいです。
集落は細かい閉じの密集したいで、木造住宅密集地域になっています。myパートナーが来て道に迷うような地域で他所の人間には用が無い場所です。隣の家が外出しているときに電話が鳴ったとするとその電話に出る文化が子供のころありました。
佐藤:野間宏と沖浦和光著『日本の聖と賤』四部作を愛読しているので、賤民たちのことは知識では知ってました。が、賤民・当事者には会ったことはないです。漁民や山に暮らしたサンカや赤鬼だと思うタタラ民などです。私が見たのは、身の回りに居たのは敗戦帰国民、満州からの引揚者たちが移民となり地域の山奥で暮らしていました。その子供たちは義務教育の場にはいました。年が経て、彼ら引揚者の一部子孫たちは原発事故後、放射能沈着し避難先の福島市民から虐めに遇ってました。(映画:『津島』 土井敏邦作品予告編と シンポジューム記録)
タント:都内では住宅の「住みひらき」とか、「コミュニティーをつくろう」と言います。コミュニティーデザインという言い方もあります。「住みひらき」、と言わなきゃいけない程度にバリヤーを張っているのが、東京の町に住んでいる人なのかなと思います。自然発生的に普通に集落が出来ていたら、「住みひらき」しなくっても成立するのではないかと思っています。コミュニティーデザインと言うけれど、ゼロからコミュニティーはつくれない。そのコンテクストを分かるには東京からやって来て、1,2年では分からないと思います。
G父の事業整理で地元に入って、その地縁の中に入っていけないので、それを痛感しています。要するに私も「東京の」零細民なのだということを思いました。
鍵を渡して平気じゃないとコミュニティーの中には入っては行けない、そう思っているんです。コミュニティーデザインと言う人は流行だけどあまり、気が向かないですね。
佐藤:今は町内会とはいうが、真の地域のコミュニティーは私の身の回りにもないです。で選択縁とでも言うのでしょうか大阪でも都内でも部屋の「鍵」をくれる友達は居ます。泊まり歩いてましたが、最近は体力と足代が貧しくなったので、遠くの地へ行くことは少なくなりました。タントさんが言う自然発生的なコミュニティーの様子は分かる、最後の世代だと思ってました。
タント:だから電話を本当に取るんですよ。漁村なので祭りになると、土間があってそこに家主がいなくっても近所の人が4〜5人いることがあります。先般訪ねた新築住宅に行ったときに、「所有者は隅々まで見せる方だ」と言ってその先輩が笑ってましたが、普通なんじゃないかなと思いました。自宅に他人が居るというのは変なことではないと思ってます。田舎だったらそういうことはよくあります。
作家の中島らものエッセーでは自分の家にいろんな不良が住んでいて、彼らの出入りは気にしなかった。小津安二郎の映画を観ても勝手に人が泊まりくるシーンがあるので、家の中に自分たちが知っている人しか居ないという状況の方が異常なんじゃないかなと思います。
■建築あそび
佐藤:リリーフランキー著『東京タワー』は彼の自伝的小説ですけれど、笹塚の家にかぎらず友達が住み込んでてリリーさんの母親の料理を御馳走になって、母親は実の子供のような扱いをしていたとあります。私は1984年秋に自邸が完成した直後から、定期的に開放し他者を招きいれるために「建築あそび」と名づけてイベントをやってました。webが使われるようになった2000年頃からはそこで語り合った内容の一部を記録として公開し始めました。
タント:あれ(建築あそび)はいいなと思ってました。
佐藤:そうですか。役所支援のそのような出来事は多くなりましたが、個人がささやかに背伸びせず、自前手作りの建築あそびを持って活動することを推します。
現在は、2007年に妻の症状と講師の症状が悪化して、大混乱しました。で、自宅での開催は一端あきらめて、その後は私が出かけて他者の家を借りて、人を招いてその地で建築あそび=「ことば悦覧」を開催していました。(web記録は「ことば悦覧」と題し公開中)
都内の家を開放した話がでましたが、隅々まで開くなどという言葉では説明して成るものではないし、自然に集まって語り合いが始まるものだと思います。建築家の説明は頭で考えて押し付け気味、自然発生したものではないことでしょう、タントさんが仰るコミュニティーの様とは違う、プロ役者の演技に近いですね。本当に根付いているなら、言葉での説明は要らないでしょうね。
設計事務所の場を借りて他者を招いて呑みながら、ワイワイしたことも数度あります。京都では川勝真一さんの家でワイワイ(記録へ)、大阪の家成俊勝さんのドットアーキテクツに森純平さんを招いてワイワイ(記録へ)。東京でも神田の竹内泰先生の事務所「あび清}に種田元晴さんを招いてワイワイ(記録へ)などで、他者の所有する場を使わせていただきました。
タント: 家の中に誰でも入っているという話をしましたが、それでも本当に大切なものは、見せないところ、わからないところに隠すと思います。
佐藤:共同体の家は同じプランで作られていて、似たような家と家だったと思います。建築家と称する者たちがつくる建築プランは個性的で共有しにくい、その問題もありそうですね。(省略:先日の東京イベントの問題点を語りあう)
タント:ヨーロッパには「見せ部屋」の文化があると聞きました。例えばイギリスだったら家でも見えるところはネクタイしてご飯たべる、そういう文化がある。そういう「見せ部屋」的なものをあまり考えず日本に持ち込んだような住宅はあまり好きではありません。
地元の家のプランは外から見て分かります。伝統的な日本の集落それに、日本の中間層以下が住んでいる住宅のプランはパターンがあるので、外から見ても分かりますよね。そしてインターネットで上から観たらこれはこうなっているだろうなと想像もつきます。他人が中に入らなくっても中身が分かるのに、それを隠したくなる程度に、隣人や町内、あるいはコミュニティー内部で信頼がないのだろうと思います。
佐藤:建築設計などを生業としていたので、設計士の説明や解説と目の前の建物の事実は違うことが分かるから、悲しいですね。いわゆるプロの言葉を素直に受け止められなくなる。一種の病気でしょうかね。
■輪中
佐藤:話を変えましょう、タントさんの地元はリアス式海岸ではないですよね。
タント:輪中です。島になっているけど、海や川より低くなっているので、堤防に囲まれていて、そこに住んでいる。そういう島がいっぱい集まっている所だった。で、中世では権力が及ばないようなエリアになっていました。
今では河川改修工事が進んで干拓になっています。単にゼロ・メートル地帯ですが、郷土教育では水難についての歴史教育が盛んでした。
輪中の町海津に関する動画
佐藤:港町や東海道も含め近世期の宿場町は売春文化がセットでした。そういう場所でしたか?
タント:戦前の盛り場ですから、そういう文化はあったと思います。魚を獲った後に対岸に渡っていった(笑)という話を聞きます。
城下町の方ではかなり大きな遊郭があり、戦前の観光案内ではかなりの分量を占めていますが、今でも誰も知らない話です、私の小学校の時の友人の家が、今思えばまさに「そういう宿」の建築でしたが「旅館だった」と言ってました。現在では旧赤線を巡る女性が増えていると聞きましたが、心情が理解できません。
佐藤:中上健次の小説を読んで育った?それはなかったですか。
タント:ああいう暴力性はないです、あのような閉塞感みたいなのはあるんじゃないですかね。自分の性格もあって、そういうふうに感じます。
佐藤:タントさんには自覚はないんだろうけど、元来、地域の縁が深いところで育ったんですね。日本列島にそのような場所を作ろうとしても、もう出来ないですし、古い地域性があっても、原発事故後、後期資本主義のもとにある現代建築を学んで町づくりしているのを見ると、事故前の日本人には合わないなと思います。それをタントさんは分かる、と思います。都心で育ち近代建築を学んだ若者にはタントさんの思いは聞かせても理解できていないでしょう?
■建築学科へ(日本建築史を学ため)
タント:学部4年生の研究室配属では建築史の研究室に入ったんです。その後大学院は出身大学とは違う東大に入れてもらいました。
佐藤:建築科に入ろう!とした動機はなんですか?
タント:建築家になろうとは思っていなく、唐招提寺を観ていいなと思いました。最初から建築の歴史をやろうと思ってました。認識できない程度に昔からそこに同じ建物があるということにナイーブに感動してしまいました。そういうわけで最初から建築の歴史を勉強したくて建築学科にはいりました。構造力学の歴史も面白くってガリレオの『新科学対話』もよみました。
設計製図の成績はそこそこよかったんです。理由はアトリエ事務所の先生に迎合していて、こうすればいい建築じゃん、と。それらしき物体状のものを作って、それから図面を起こせば・・・いい点くれるんだと思ってました。セコい考えになってまして、これは実務家になったらろくでもない奴になるなと思いましたので歴史で間違いないと思いました。
大学院になる頃には、都市史という分野を知って、自分の育ってきた地域や場所が伝統的建造物群じゃんと思ったんです。
佐藤:説明を聞いた限り、輪中にある伝建地域ですね。その生活を知らないで育った研究者と違った。その地域で育った実体験あって凄い研究者としては、ラッキーでいいですね。
タント:そこで網野善彦を読みました。祖母の家の屋根に入ったら木材に「ちょうな」が掛けてあったんです。祖母の家は江戸時代に建てたようなものではなく、アメリカの空襲(太平洋戦争)で焼かれた後に建てられた復興建築というべきものです。が、おそらく、前身建築とプランも変わらない、古材を使ったものです。「家の建て替えは同じプランになるにきまっている。」そういう感覚があります。
住宅の平面にバリエーションはあまりなく、変化も劇的に起こらないと、考えているので、予期せぬプランが提案できる建築家は創造性に満ちた人なのだろうと思います。
佐藤:なるほど、でも俺は突拍子もない建築を設計してきたけど、発注者の暮らしを観察して暮らし方、身に付いた癖を知り尽くしてから、ここまで変えても大丈夫だ・・・と分かったら、実施設計を始めてました。いきなり突拍子もない提案しても住みこなせないはずです。生活に無理が掛かってしまいます。だから住宅には成らないですね。観るだけの建築だったらそれでもいいんだけど。発注者の前の暮らしを引き継いで突拍子もない建築でも暮らせる、突拍子の限界を見極めて提案して、そこから造ることが肝心だ、と思います。ベースの建築での暮らし、それを観察せず、突拍子もない建築で暮らせというのは暴力と拷問になりますので、慎むべきですよ。
タント:建築家は、次にどうやって驚かすかを常に考えている人種なので(笑)。
佐藤:雑誌を手に取って楽しむ者はそれでいいだろうけど、発注した者はどうにも暮らせないじゃないですか? ゼネコンで10年設計部にいたので、突拍子もない建築には人は暮らせない、と思ってました。だから発注者のもとの暮らしを隅々まで観察してから、設計を始めていました。
タント:そうだと思います。ドイツの雑誌から問い合わせが来た、というタウトのような建築を佐藤さんは設計してますけど、─タウトと別に考えなきゃいけないんですけど─、幻想的な所に住めていて、それで生活が成り立っているなと思うのはいいなと思いました。
佐藤:あの建築についても植田実さんが解説を書いて1994年、『建築文化』に特集されて掲載されています。植田さんの解説を読むとあの建築を理解していると分かりました。他の建築関係者は理解してなかったです。奇をてらって作っているとしか思ってなかったです。山登りが好きな発注者の暮らし方をままあの建築に変換しただけなんですから、彼らにとっては奇異な建築ではなく、当たり前のように愛犬を放ち、無理なく自然に暮らしていました。だいぶ昔の事なので詳細は忘れてしまいました。発注者が突拍子も無い?・・・ことを言うので、それの内容に沿って作るとそうなるだけで不自然ではないですよ。
山登り好きだというから身近にある安達太良山(通称・乳首山)を移植しただけ。それは変わっていたかもしれないけど、依頼者は山登り好きなので内外を登って楽しんでいるとは聞かされましたが、見に行ってないです。乳房の部分はガラスとステンレスを鱗状に組み合わせました。太陽が移動しますので、それぞれの硝子から光が入り干渉し合うので、光の濃淡が映し出され日常にはない4帖半になるので、まま幻想的でした。太陽が移動するだけでそうなるんです単純なんです。暮らしの地べた部分と地上の象徴的な部位とは切り分けてあるんです。地球の自転を小さな建築に写し転用しただけです。
タント:タウトのガラス・パビリオンですね、
佐藤:それを知らなくって設計したんで、後で雑誌社の方に教えてもらいました。タウトとどこが似ているのかは調べてません。もし偶然似たなら、それは仕方のないことです。今のようなことは誰にも説明しなかったです。自分一人で喜んでいたんです、発注者の意図を咀嚼しちゃっているので、使う人は自由に使用方法を発明する、完成後は問題ないです。グリコのおまけを家にくっつけたようなものです。
タント:グリコのおまけじゃないですよ、発注者としてはこれがないと嫌ですよ。
佐藤:my建築の話をしちゃいましたけど、これでやめましょう。
タウト:人間は逃げ込む所が必要だと思います。私の家はありきたりな共同住宅で、おうちでどこに行っても均質です。僕の雑多な本が積み上げてある部屋も、台所も、寝る部屋も、全部同じ様相をていしていて、変化がない。変わりばえのしない時間と空間があります。こういう状態だと気持ちがどんよりしてきます。
私はそもそも生きていて楽しくないので、家がもっと楽しくないということになってしまいます。そういう時にキラキラした所に逃げ込みたいですよ。建築論じゃなくって、単純にこれをぱっと見た時にこの4帖半の丸い部屋でキラキラしているものがある。そういうものが自宅にあるというだけで、ご機嫌な気分になれるのではないかと思いました。
佐藤:少し続けると生活空間からは見上げても見えないような丸い4帖半になっています。声は聞こえますけれど、陽射しがあれば丸い4帖半には光の揺らぎがつくる像が常に現れます。
タント:逃避場所があるわけですね。
佐藤:逃避場所というか、おまけ部屋は必ず設計してました。狭い敷地の場合は一度屋上に出てから、再度天辺の2帖離れに入るように構成してました(記録へ)。わが家は半地下と離れがあります。どちらにも逃げ込めますね。目的合理で部屋がすべて説明できるのは窮屈です。何この部屋は?という場所は要る。物を持ちこめない小さな入口の小さな1.5帖ほどの部屋もつくりましたが、なぜか籠って祈りをつづけてしまい新宗教の信者になっちゃった!そういう発注者もいました。体感で伝わってきてたんですね、あるべきだと思い造るんですが使われ方を見て驚きました、神さまと対話する部屋だった。設計建物の威力は設計した者にも分からないことが起きますよ。そういう設計ばかりしてたので、仕事がこなくなりました(笑。
タント:『千万家(せんまんいえ)』でしたか。あれも発想が大変おもしろいですよ。
佐藤:植木屋さんから電話掛かってきて、聞いてたら直ぐできました。模型をつくりこれでいいよ、はいと渡しました。これで建てよう!と言ってました。各種法律、調整区域と開発と農地転用が絡んでいたので、工事始まるまで4年間かかりました。1/100の模型は電話聞いてできちゃったんだけど、着工するまで4年間かかったから可愛そうだからね、1/50の模型を作って、電車Nゲージ用ライトを模型に仕込み作りました。くじけそうになったら、部屋の電気を全部消して、電池をつないで模型内ライトを灯す。それを暗い部屋で観続けていると元気がでるからと模型を竣工時まで貸しておきました。建てようという気分が湧き上がるんです。完成したときに模型を回収したんですけど、真っ黒でした(笑)。
タウト:それにしても、オンラインのカメラの向こうから佐藤さんの元気が伝わってきます。今日の1日分のエネルギーを注入してもらいました。
佐藤:そうなの?俺にとっては千万家も過去の建築も日常で平凡なことでした。昔・考えて設計したという出来事ですが、話をしていて、タントさんが元気になったなら、いいですね。
その2 (寺山修司好きの語りに続く)